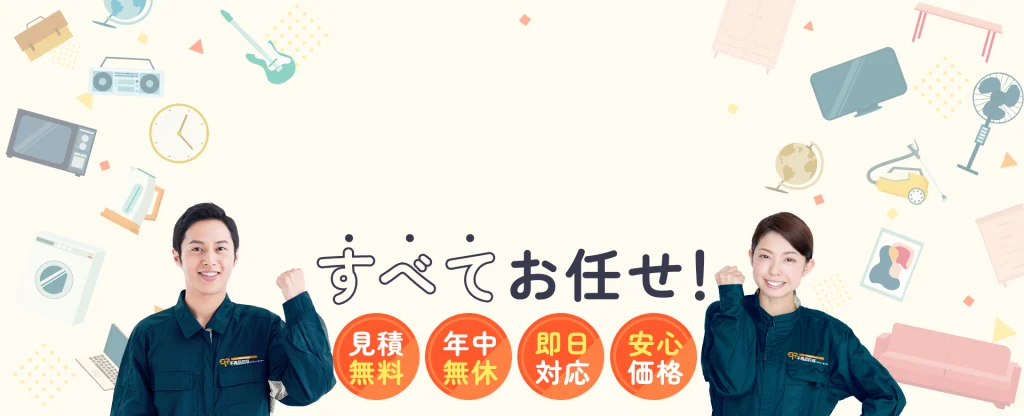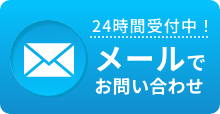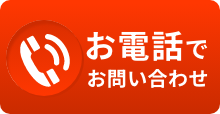【法人向け】キャビネットの処分方法の全手順と費用、会計処理まで徹底解説!
オフィスの移転やレイアウト変更で、不要になったキャビネットの処分にお困りではありませんか?法人が事業で使用したキャビネットの処分は、家庭ゴミとは全くルールが異なります。
企業のコンプライアンスにも関わる「法律問題」です。万が一、不適切な方法で処分してしまうと、会社が厳しい罰則を受けるリスクさえあります。
この記事では、企業の総務・管理部門のご担当者様が、安心して、そして賢くキャビネットを処分できるよう、法的な基礎知識から具体的な4つの処分方法の比較、信頼できる業者の選び方、さらにはコストを抑えるコツや社内での稟議・会計処理の方法まで専門家の視点から全手順を徹底的に解説します。
最後まで読めば、あなたの不安は解消され、自信を持ってこの業務を完遂できるはずです。
キャビネットの回収は不用品回収レスキューセンターにお任せください。お急ぎの方には即日対応も可能です。無料でお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にお電話、メール、またはLINEでご連絡ください。
この記事のポイントは?
なぜオフィスのキャビネット処分は法律問題なのか?

事業活動から出る廃棄物は「事業系ごみ」と呼ばれ、家庭ごみとは明確に区別されます。そして、その処理には法律に基づいた厳格なルールが定められているのです。
このセクションでは、まず担当者として絶対に押さえておくべき法的な大原則を解説します。
キャビネットが産業廃棄物になるかどうかの決め手は素材
まず理解すべきは、事業系ごみがさらに「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に大別されるという点です。そして、どちらに分類されるかは、キャビネットの「素材」によって決まります。
多くのオフィスで利用されているスチール(金属)製や、プラスチック製のキャビネットは「産業廃棄物」に分類されます。一方、100%木製のキャビネットの場合は「事業系一般廃棄物」となります。
なぜこの分類が重要なのでしょうか。それは、産業廃棄物を収集・運搬するには都道府県知事の許可を得た「産業廃棄物収集運搬業許可」を持つ業者にしか依頼できないからです。
一方で、事業系一般廃棄物は、市町村の許可を得た「一般廃棄物収集運搬業許可」を持つ業者でなければ扱えません。
もしオフィスに金属製と木製のキャビネットが混在している場合、両方の許可を持つ業者に依頼するか、別々の業者に手配するという複雑な対応が必要になる可能性も出てきます。この違いを最初に理解しておくことで、業者選定の際に「当社の金属製と木製のキャビネット、両方とも法令に則って処分できる許可をお持ちですか?」という的確な質問ができるようになります。
排出事業者責任:もし委託した業者が不法投棄したら?
「お金を払って業者に任せたのだから、あとは業者の責任」と考えてしまうのは非常に危険です。廃棄物処理法には「排出事業者責任」という大原則があります。
これは、廃棄物を排出した事業者(つまり、あなたの会社)が、その廃棄物が収集運搬され、最終的に適正に処理されるまでの一連の過程すべてに責任を負うというものです。
もし、依頼した業者がコストを浮かせるために預かったキャビネットを山林などに不法投棄した場合、その業者だけでなく、排出事業者であるあなたの会社も法的な責任を問われます。廃棄物処理法には厳しい罰則が定められており、最悪の場合、法人に対して1,000万円以下の罰金、担当者個人にも5年以下の懲役が科される可能性があります。
したがって、「とにかく安いから」という理由だけで、許可を持たない無許可の業者に依頼することは最大級のリスクと言えます。コンプライアンスを遵守し、企業の信用を守るためには、適正な許可を持つ信頼できる業者を正しく選ぶことが絶対条件となるのです。
マニフェスト制度は法的な盾であり適正処理の証明書
「では、どうすれば適正に処理されたことを証明できるのか?」という疑問に答えるのが、「産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)」という制度です。これは、産業廃棄物の流れを排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者で管理・追跡し、不法投棄を防ぐための仕組みです。
このマニフェストは、単なる事務的な伝票ではありません。これは、あなたの会社が「排出事業者責任」を果たし、法令を遵守して適正に処理を委託したことを証明する法的な盾です。
万が一、後から処理について疑義が生じた場合でもマニフェストが決定的な証拠となります。受け取ったすべてのマニフェスト伝票は、法律により5年間の保管が義務付けられています。
近年では、紙の伝票のやり取りをなくし、効率化と透明性を高める「電子マニフェスト」も普及しています。
【比較】法人向けキャビネットの現実的な処分方法4選

法的な前提を理解した上で、企業の担当者が選択できる現実的な方法は、大きく分けて4つです。ここでは、それぞれの方法のメリット・デメリットを比較し、自社の状況(緊急度、数量、予算、手間)に最適な選択ができるよう情報を整理します。
なお、「自治体の粗大ごみ収集」は事業系ごみには適用されないため、選択肢から除外して考えることが重要です。
| 処分方法 | 産業廃棄物処理業者 | 不用品回収業者 | オフィス家具買取業者 | スクラップ業者 |
|---|---|---|---|---|
| 最適なケース | 大量のキャビネットやオフィス全体の廃棄物を一括で厳格に法規通り処分したい | 少量~中量のキャビネットを手間をかけずスピーディに処分したい | 有名メーカー製で状態の良いキャビネットがあり、少しでも処分コストを相殺したい | 大量のスチール製キャビネットのみを処分し、資源として売却益を得たい |
| 費用感 | 高めだが透明性が高い | 中程度(パック料金でお得になることも) | 費用が相殺され、プラスになる可能性も | 鉄の相場により収益になる可能性 |
| スピード | 要スケジュール調整 | 最短即日も可能 | 査定・交渉に時間がかかる | 要スケジュール調整 |
| 手間 | 低い | 非常に低い | 高い(清掃、査定対応、交渉など) | 高い(自社での運搬が必要な場合も) |
| 重要ポイント |
|
産業廃棄物収集運搬業許可の有無を必ず確認 |
|
|
最もバランスの取れた選択肢:不用品回収業者を利用するキャビネット処分ガイド
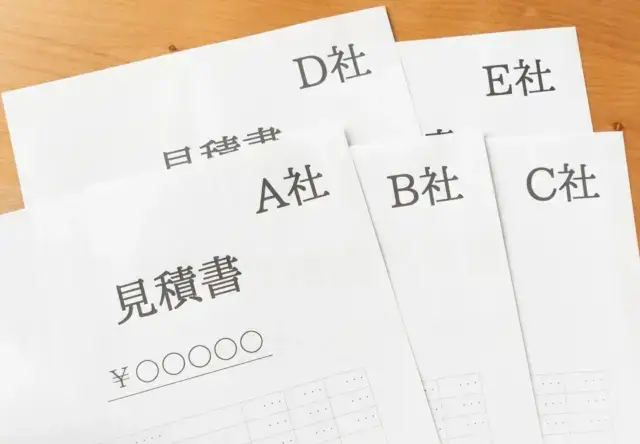
多くの中小企業にとって、スピード、手軽さ、そしてコンプライアンスのバランスが最も取れているのが適切な許可を持つ「不用品回収業者」を利用する方法です。ここでは、失敗しないために、業者選定から作業完了までの具体的なステップを解説します。
1:情報収集と事前準備
業者に連絡する前に、いくつかの情報を手元にまとめておくと、その後の見積もりや相談が非常にスムーズに進みます。まず、処分したいキャビネットの以下情報をリストアップしましょう。
- 台数
- 種類(例:3段スチール書庫、木製両開きロッカーなど)
- おおよそのサイズ(高さ・幅・奥行き)
- 設置場所(例:ビルの5階、エレベーター有り)
次に、スマートフォンのカメラでキャビネットの写真を撮っておくことをお勧めします。これにより、電話やメールでの問い合わせ時に、業者が状況を正確に把握しやすくなり、より精度の高い概算見積もりを得ることが可能になります。
2:残置書類の確認
非常に重要な点として、キャビネットの中に書類などが残っていないかを確認してください。特に機密情報や個人情報が含まれる書類は、キャビネットとは別に専門の機密文書溶解サービスなどを利用して処分する必要があります。
不用品回収業者の中には、こうした機密文書処理サービスを同時に手配してくれるところもありますので必要であれば相談してみましょう。
3:業者の検索と信頼性のチェック
依頼する可能性のある業者を探します。インターネットで「オフィス家具 処分」「産業廃棄物 回収 (あなたの市区町村名)」といったキーワードで検索するのが一般的です。
しかし、見つけた業者にすぐ連絡するのではなく、必ず信頼性をチェックするステップを踏んでください。
最も重要なチェック項目は、その業者が「産業廃棄物収集運搬業許可」を正式に取得しているかです。この許可は都道府県が発行するもので、信頼できる業者は必ず公式サイトの会社概要ページなどに許可番号を明記しています。
許可番号が見当たらない場合は、必ず電話などで直接確認しましょう。
あわせて、会社のウェブサイトに物理的な住所(所在地)と固定電話の番号が記載されているかも確認してください。連絡先が携帯電話番号のみの業者や住所が曖昧な業者は、トラブルが発生した際に連絡が取れなくなるリスクがあるため避けるのが賢明です。
4:見積もりの依頼と比較(相見積もり)
信頼できそうな業者を2~3社リストアップしたら、それぞれに見積もりを依頼します。これを「相見積もり(あいみつもり)」と呼び、適正な市場価格を把握し、不当に高い料金を請求されるのを防ぐために不可欠なプロセスです。
この際、ただ総額を比較するだけでは不十分です。
優良な業者が提示する見積書には、以下のような料金の内訳が明確に記載されています。
- 基本料金
- 作業員の人件費(人数と時間)
- 車両費
- 品目ごとの処分費
- その他オプション料金(階段作業、解体作業など)
逆に、「作業一式」として総額しか書かれていないような、内訳が不透明な見積書を提示する業者には注意が必要です。後から「これは追加料金です」と言って、想定外の費用を請求されるトラブルの原因になりかねません。
不明な点があれば、契約前に必ず質問し、納得のいく説明を得ることが大切です。
5:作業当日と最終確認
契約した日時に、業者の作業員がオフィスにやってきます。プロの作業員は、建物の壁や床を傷つけないよう、必要に応じて保護シートなどで「養生」を行い、迅速かつ安全にキャビネットを搬出します。
作業が完了し、業者がキャビネットを運び出す直前に、担当者として最も重要な仕事が待っています。それは、マニフェスト(A票)の受け取りです。
業者は持参したマニフェストに必要事項を記入し、あなたのサインをもらった後、1枚目のA票をその場であなたに手渡します。これが、法的に「廃棄物の引き渡しが完了した」ことの証明になります。
このA票を受け取るまでは、絶対に作業完了と認めてはいけません。
A票を受け取ったら、料金を支払い、必ず「領収書」を発行してもらいます。その後、受け取ったA票は社内で大切に保管し、後日郵送されてくるB2票、D票、E票を待ちます。
これらすべての伝票が揃って初めて、あなたの会社の法的責任が完了したことになります。
キャビネット処分の費用内訳

不用品回収業者に支払う料金は、いくつかの要素で構成されています。この構造を理解することで、見積もりの妥当性を判断し、交渉の余地を見出すことができます。
品目ごとの処分料金
これが費用の基本です。キャビネット1台あたり、サイズや種類にもよりますが、おおよそ3,000円~7,000円程度が目安となります。
車両費(トラック料金)
業者が使用するトラックのサイズに応じた料金です。処分する量が多い場合は、「軽トラック積み放題プラン:33,000円~」といった定額パックを利用した方が、個別に計算するより割安になることがあります。
人件費(作業費)
作業員の数と作業時間によって算出されます。1人1時間あたり3,000円~5,000円が相場です。
搬出経路が複雑な場合、解体が必要な場合は、作業員が増えたり時間がかかったりするため費用が加算されます。
オプション料金
基本料金に含まれない追加作業の費用です。代表的なものに以下があります。
- エレベーターがない場合の「階段料金」
- オフィス内での「解体作業費」
- 夜間や早朝に対応してもらう場合の「時間外料金」
見積もり時に、こうした追加料金が発生する可能性がないか、事前に確認しておくことがトラブル回避の鍵です。
買い取りで費用を相殺
処分費用を少しでも抑える有効な手段が「買取」です。ただし、どんなキャビネットでも買い取ってもらえるわけではありません。
まず現実として、一般的なオフィスで長年使われたノーブランドのスチールキャビネットは、買取価格がつかないか、ついてもごく僅かであることがほとんどです。買取の目的は「利益を出す」ことよりも「処分費用を相殺する」ことにあると考えるのが現実的です。
買取価格が期待できるのは、以下のような条件を満たす場合です。
- オカムラ、コクヨ、イトーキといった国内トップブランドの製品
- 傷やへこみが少なく、日焼けやサビがない良好な状態:
- 書庫の棚板や、引き出しの鍵など付属品の完備
- メーカーやモデルが同じ
- 一般的に製造から5年以内のもの
不用品回収業者の中には、処分と買取を同時に行ってくれるところも多くあります。処分したいキャビネットの中に価値のありそうなものがあれば、査定を依頼し、買取額を処分費用から差し引いてもらうことでトータルのコストを賢く抑えることが可能です。
キャビネット処分の会計処理
キャビネットの処分は、業者の手配が完了すれば終わりではありません。処分の事実を経理部門に報告する際、適切な会計処理の方法を把握していると連携がスムーズになります。
キャビネットの処分にかかった費用は、経費として計上します。その際に使用する勘定科目は、主に以下のいずれかです。
| 勘定科目 | 注意点 |
|---|---|
| 支払手数料 | 単発のキャビネット処分であれば、この科目が最も一般的 |
| 外注費 | もし会社が定期的に廃棄物処理を外部委託しているのであれば、こちらが適切な場合があります。 |
| 雑費 | 他のどの勘定科目にも当てはまらない、少額で重要性の低い経費 |
もし、処分するキャビネットが会社の「固定資産台帳」に資産として計上されている場合、もう一つ重要な会計処理が必要になります。それが「固定資産の除却」です。
これは、帳簿上からその資産を消し、その時点での帳簿価額を「固定資産除却損」という損失として計上する手続きです。処分業者からの領収書とマニフェストがあれば、経理部門は必要な処理を滞りなく進めることができます。
まとめ
この記事では、企業の担当者様がオフィスのキャビネットを処分する際に直面する、法的な課題から実務的な手順、コスト管理に至るまで解説してきました。
最も重要なメッセージは、法人のキャビネット処分は、単なる「片付け」ではなく、企業の信用とコンプライアンスに関わる「法務案件」であるという認識を持つことです。複数の業者から透明性の高い見積もりを取り、買取サービスなども活用して、コストと手間、安全性のバランスが取れた最適な方法を選択しましょう。
もし、信頼のパートナーをお探しでしたら、ぜひ私たち不用品回収レスキューセンターにご相談ください。透明性の高いお見積もりから、マニフェストの発行、買取のご提案までお客様の状況に最適なプランをご提供し、安心の処分プロセスをワンストップでサポートいたします。
お見積もりは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。電話、メール、LINEで24時間365日対応しております。
よくある質問
オフィスにスチール製と木製のキャビネットが混在しています。何か注意点はありますか?
両方の許可を持つ、信頼できる不用品回収業者に依頼するのが、一度の手配で済む最も確実で簡単な方法です。
ある業者からの見積もりが、他社に比べて極端に安いのですが、大丈夫でしょうか?
- そもそも許可を持たない無許可業者で、不法投棄を前提としている
- 基本料金を安く見せかけ、作業当日になってから「階段料金」「解体費」などと称して高額な追加料金を請求する
企業の法的安全性を最優先し、料金の安さだけでなく、許可の有無、見積もりの透明性、会社の評判を総合的に判断してください。
キャビネットの中の機密書類を処分する最も安全な方法は何ですか?
処理後には「溶解証明書」が発行され、これもまた企業のコンプライアンスを証明する重要な書類となります。多くの不用品回収業者は、この溶解処理サービスも提携しており、オフィス全体の片付けの一環として手配可能です。