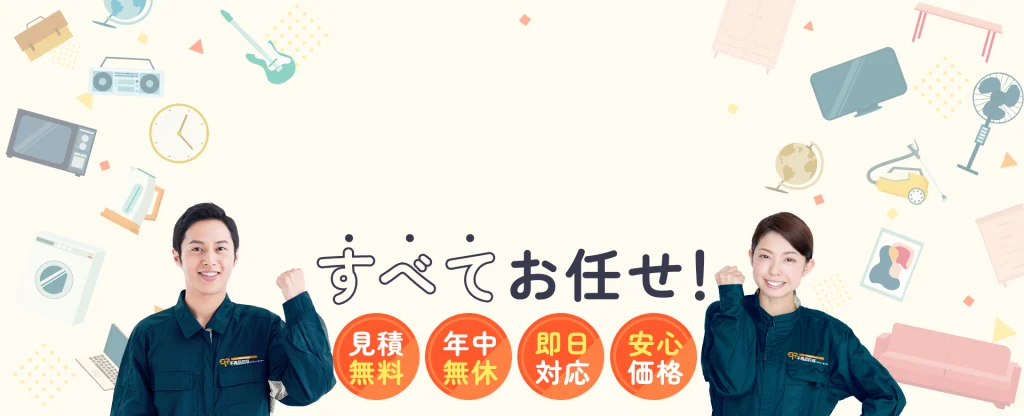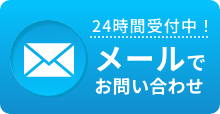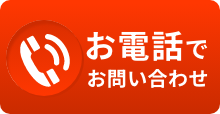実家じまいの費用はいくら?解体・片付けの相場、安く抑える方法までプロが徹底解説!
親御さんの家を片付ける「実家じまい」。思い出の整理という感傷的な側面に加え、「一体いくらかかるんだろう?」という現実的な費用の不安が、重くのしかかっていませんか?
実家じまいの費用は、家の状況や選択によって数十万円で済むこともあれば、解体や売却が絡むと1,000万円を超えるケースも珍しくありません。何にいくらかかるのか、どうすれば費用を抑えられるのか、情報が多すぎて混乱してしまうのも無理はないでしょう。
この記事では、実家じまいで発生しうる全ての費用を項目別に分解し、それぞれの相場を具体的に解説します。さらに、使える補助金制度や賢い業者の選び方、そして意外な落とし穴まで専門家の視点から徹底的に掘り下げます。
実家じまいは不用品回収レスキューセンターにお任せください。お急ぎの方には即日対応も可能です。無料でお問い合わせいただけますので、まずはお気軽にお電話、メール、またはLINEでご連絡ください。
この記事のポイントは?
実家じまいの費用4つのパターン別総額目安

実家じまいと一言でいっても、その内容はさまざまです。賃貸物件を引き払うのか、持ち家を売却するのか、あるいは解体して土地として活用するのか。最終的に「実家をどうするか」によってかかる費用の総額は大きく変わります。
まずはご自身の状況がどのパターンに近いかを確認し、費用の全体像を掴みましょう。
| シナリオ | 主な作業内容 | 費用の総額目安 |
|---|---|---|
| 賃貸物件の片付け |
|
20万円~80万円 |
| 持ち家の片付けのみ |
|
15万円~100万円 |
| 持ち家をそのまま売却 |
|
50万円~数百万円(売却価格による) |
| 持ち家を解体して売却 |
|
200万円~1,000万円以上 |
これらの費用はあくまで目安です。しかし、実家じまいが「家財の片付け」「不動産の処分」「各種手続き」という複数のフェーズで構成されていることがお分かりいただけたかと思います。
これらの費用内訳を一つひとつ、詳しく掘り下げていきます。
家財の片付け・処分費用
実家じまいで誰もが最初に着手するのが、家の中に残された家財道具の片付けです。
片付けを業者に頼むとき、選択肢は主に「不用品回収」と「遺品整理」の2つです。この2つは似ているようで、サービス内容と費用が大きく異なります。
| 不用品回収 | 遺品整理 | |
|---|---|---|
| サービス概要 | 「不要な物」を回収するサービス | 故人の残した品々を「遺品」として丁寧に扱い、必要な物と不要な物の仕分けから手伝ってくれるサービス |
| ユーザー側の作業 | あらかじめご自身で必要な物と不要な物を仕分けておく必要 | 基本的になし 貴重品の捜索や供養、簡単な清掃まで業者が行う |
| 費用目安1R・1K | 1.5万円~8万円 | 3万円~10万円 |
| 1LDK・2DK | 3.5万円~25万円 | 7万円~25万円 |
| 2LDK・3DK | 5.8万円~30万円 | 12万円~40万円 |
| 3LDK・4DK | 8万円~50万円 | 17万円~50万円 |
| 4LDK以上 | 20万円~(要見積) | 22万円~(要見積) |
どちらを選ぶかは、ご自身の時間的・精神的な余裕によります。「すでに貴重品や思い出の品の整理は終わっていて、あとは残った物を処分するだけ」という状況なら、コストパフォーマンスの良い不用品回収が適しています。
一方で、「どこから手をつけていいか分からない」「大切な書類がどこにあるか不明」といった場合は、遺品整理サービスを検討するのが良いでしょう。この違いを理解することが、適切な業者選びと費用削減の第一歩です。
この基本料金に加え、エアコンの取り外しや、階段での搬出(2階以上)、ピアノや金庫といった重量物の運搬には追加料金が発生することがあります。見積もりを取る際には追加費用の有無を必ず確認しましょう。
建物の解体費用
家が古い、あるいは売却が難しいといった理由で更地にする場合は高額な解体費用が発生します。この費用は、建物の構造と広さ(坪数)によって大きく変動します。
一般的に、解体費用は「木造 < 鉄骨造 < 鉄筋コンクリート(RC)造」の順に高くなります。頑丈な建物ほど解体に手間と時間がかかるためです。
| 構造 | 1坪あたりの単価目安 | 30坪の場合の費用相場 | 50坪の場合の費用相場 |
|---|---|---|---|
| 木造 | 3万円~5万円 | 90万円~150万円 | 150万円~250万円 |
| 鉄骨造 | 5万円~7万円 | 150万円~210万円 | 250万円~350万円 |
| RC造 | 6万円~8万円 | 180万円~240万円 | 300万円~400万円 |
付帯工事費
解体費用の見積もりで注意したいのが、「付帯工事費」です。これは建物本体以外を撤去するための費用で、見積もりに含まれていない場合があります。
| 付帯工事 | 費用目安 |
|---|---|
| ブロック塀、門、フェンスの撤去 | 1㎡あたり5,000円~10,000円程度 |
| 庭木、庭石の撤去 | 庭木1本あたり数千円~数万円 庭石は大きさにより変動 |
| カーポート、物置の撤去 | 数万円程度 |
| アスベスト除去 | 数十万円 |
古い建物の場合、断熱材などにアスベストが使われている可能性があります。法律で除去が義務付けられています。
解体業者に見積もりを依頼する際は、これらの付帯工事が含まれているかを必ず確認しましょう。
解体後の固定資産税の罠
ここで非常に重要な注意点があります。家を解体して更地にすると、翌年から土地の固定資産税が大幅に上がる可能性があるのです。
住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、税金が最大で6分の1に軽減されています。しかし、建物を解体するとこの特例が適用されなくなり、税金が6倍に跳ね上がってしまうのです。
したがって、「とりあえず解体しておく」という判断は危険です。土地の売却先が決まるなど、具体的な計画が立つまでは建物を残しておく方が税金面で有利な場合が多いことを覚えておきましょう。
不動産売却の費用
実家を売却する際には、売却価格の全額が手元に残るわけではありません。仲介手数料をはじめ、さまざまな諸費用がかかります。
仲介手数料
不動産会社に支払う成功報酬です。法律で上限が定められており、一般的に「(売却価格 × 3% + 6万円) + 消費税」で計算されます。
例えば2,000万円で売却した場合、約72万円の仲介手数料が必要です。
印紙税
売買契約書に貼る収入印紙代です。契約金額によって異なり、1,000万円超~5,000万円以下の物件であれば1万円です(軽減措置適用後)。
登記費用
住宅ローンが残っている場合の「抵当権抹消登記」や、司法書士への報酬などです。合わせて数万円~十数万円程度かかります。
その他
土地の境界が不明確な場合の「測量費用」(35万円~80万円程度)や、買い手への印象を良くするための「ハウスクリーニング費用」(数万円~)がかかることもあります。
税金・手続き費用
不動産の売却で利益が出た場合や、相続の際には税金がかかります。特に譲渡所得税は金額が大きくなる可能性があるため、しっかり理解しておく必要があります。
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金です。譲渡所得は「売却価格 – (取得費 + 譲渡費用)」で計算されます。
税率は不動産の所有期間によって異なり、5年を超えていると約20%、5年以下だと約39%と大きな差があります。
親が購入した当時の契約書などが見つからず「取得費」が分からない場合、税法上で売却価格の5%しか取得費として認められません。これにより譲渡所得が不当に高額になり、税金が何百万円も増えてしまうケースがあるため契約書は必ず探しましょう。
3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる非常に有利な特例があります。適用には「相続開始から3年以内に売却すること」などの条件があるため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続税
実家を含む遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税がかかります。これは売却とは別のタイミングで、相続発生後10ヶ月以内に申告・納税が必要です。
放置・維持のリスクと費用
「すぐに決断できない」「費用がかかるから先延ばしにしたい」と思う気持ちも分かります。しかし、実家を空き家のまま放置することは、実は「何もしない」という選択ではなく、「毎年お金を払い続ける」という金銭的な判断をしているのと同じです。
空き家を維持するためには、以下のような費用が毎年かかり続けます。
- 固定資産税・都市計画税:数万円~数十万円
- 火災保険料:数万円
- 水道・光熱費の基本料金:年間2万円~3万円
- 庭の手入れや小規模な修繕費:数万円~
- (遠方の場合)定期的な管理のための交通費
- (遠方で管理できない場合)空き家管理サービスへの委託費:年間6万円~12万円
これらを合計すると、年間で25万円から40万円以上の出費になることも珍しくありません。5年間放置すれば、125万円~200万円ものお金が消えていく計算になります。
さらに、放置された家は急速に資産価値が下落し、倒壊などで近隣に損害を与えた場合は損害賠償責任を問われるリスクもあります。先延ばしにすることは百害あって一利なしと言えるでしょう。
賢く節約!実家じまいの費用を抑える3つの戦略

知識を持って計画的に進めることで負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは、誰でも実践できるコスト削減の戦略をご紹介します。
補助金・助成金を活用する
費用負担を直接的に軽減できる最も効果的な方法が、自治体の補助金制度を活用することです。各市区町村が独自の制度を設けています。
最も多くの自治体で導入されているのが、老朽化した危険な空き家の解体費用に対する補助金です。
「昭和56年以前の旧耐震基準の建物」であることや、所有者の所得制限などが条件となることが多いですが、対象になれば費用の2分の1から5分の1程度、上限額にして20万円~100万円ほどの補助が受けられます。
片付け費用も補助対象になるケースが
数は少ないですが、家財の片付け費用を補助してくれる自治体もあります。これは「遺品整理」という名目ではなく「空き家の片付け」として扱われます。
多くの場合、自治体が運営する「空き家バンク」に物件を登録することが条件となります。家財の処分費用や清掃費用として上限10万円~20万円程度が補助されることがあります。
補助金を利用する上で最も重要なことは、必ず解体や片付けの業者と契約する前に自治体の担当窓口に相談・申請することです。
自分でやる作業とプロに任せる作業を分ける
全ての作業を業者に任せるのではなく、自分でできることを行う「ハイブリッド方式」も有効な節約術です。
自分でやるべきこと
貴重品や思い出の品の仕分け、自治体のルールに従った一般ゴミの分別・処分、まだ使える家具や家電の清掃などは自分で行えます。これらを事前に行っておくだけで、業者に依頼する物量を減らすことができ、結果的に費用を抑えられます。
プロに任せるべきこと
大型家具や家電の搬出、エアコンの取り外し、専門的な知識が必要な遺品の仕分け、そして建物の解体などはプロに任せるべきです。無理に自分で行うと、怪我をしたり建物を傷つけたりするリスクがあり、かえって高くつく可能性があります。
特に家財整理では、自分で仕分けを済ませた上で割安な「不用品回収」サービスを利用するのが最もコストパフォーマンスの高い方法の一つです。
複数の業者から相見積もりを取る
解体業者でも不用品回収業者でも、必ず最低3社から相見積もりを取りましょう。1社だけの見積もりでは、その金額が適正なのか判断できません。
相見積もりを取ることで、料金の比較ができるだけでなく、各社のサービス内容や担当者の対応の違いも明確になります。単に一番安い業者を選ぶのではなく「見積書の内訳が詳細で分かりやすいか」「質問に丁寧に答えてくれるか」といった信頼性も合わせて判断することが最終的な満足度に繋がります。
失敗しない業者選びのチェックリスト

実家じまいを成功させる鍵は、信頼できる専門業者をパートナーに選ぶことです。優良な業者を見極めるための絶対的な基準をご紹介します。
最重要:一般廃棄物収集運搬業許可
価格やサービス内容を比較する前に、まず確認すべきなのが法的な許可の有無です。家庭から出るごみ(一般廃棄物)を有料で収集・運搬するには、事業を行う市区町村から「一般廃棄物収集運搬業許可」を得ることが法律で義務付けられています。
この許可の取得は非常に厳しく、多くの自治体で新規発行が停止されているため、許可を持つ業者は限られています。
ウェブサイトなどで「産業廃棄物収集運搬業許可」や「古物商許可」だけを掲げている業者は、一般家庭の片付けを請け負う法的な資格がない可能性があります。
最初に「〇〇市(実家のある自治体名)の一般廃棄物収集運搬業許可はお持ちですか?」と質問しましょう。明確な回答が得られない、あるいは話を逸らすような業者は選択肢から外しましょう。
これが、悪徳業者を回避する最も確実な方法です。
買取を依頼するなら古物商許可
片付けと同時に、まだ価値のある家具や家電を買い取ってもらう場合は、業者が「古物商許可」を持っているかを確認してください。この許可なく買取を行うことは違法です。
見積もりの透明性と対応の丁寧さ
信頼できる業者は見積もりのプロセスも誠実です。以下ポイントを確認しましょう。
- 訪問見積もりを基本とする
- 見積書の内訳が明確
- 追加料金の条件を説明する
電話やメールだけで確定料金を提示するのではなく、必ず現地を訪れて物量や作業環境を確認した上で、詳細な見積書を作成してくれる業者を選びましょう。
また、基本料金、人件費、車両費、処分費、オプション料金などが項目別に記載されているか確認します。「作業一式」といった曖昧な記載しかない場合は要注意です。
そして、どのような場合に、いくらの追加料金が発生する可能性があるのかを事前にきちんと説明してくれる業者は信頼できます。
損害賠償保険への加入
作業中に万が一、家や遺品を傷つけてしまった場合に備え、損害賠償保険に加入しているか確認しましょう。
ウェブサイトの充実度
会社の所在地、代表者名、固定電話番号が明記されているか確認しましょう。また、具体的な作業実績やお客様の声が掲載されているかも判断材料になります。
遺品整理士の在籍
遺品整理を依頼する場合、「遺品整理士」という民間資格を持つスタッフが在籍しているかは、専門知識と丁寧な対応を期待できる一つの目安となります。
費用だけじゃない!実家じまいで避けるべき親族トラブル

実家じまいは、お金の問題であると同時に、家族の感情が絡むデリケートな問題でもあります。手続きを円滑に進めるためには、親族間のトラブルを未然に防ぐことが何よりも重要です。
何よりも大切なのは、実家じまいを始める前に、関係者全員で話し合いの場を持つことです。親が健在であれば親の意向を最大限尊重し、相続が絡む場合は兄弟姉妹全員の合意形成が不可欠です。
話し合いで決めておくべきことは以下の通りです。
- なぜ実家じまいをするのか、最終的に家をどうしたいのか(売却、解体、誰かが住むなど)の方向性を共有する
- 誰が、どの費用を、どのくらいの割合で負担するのかを明確にする
- 誰が中心となって手続きを進めるのか、誰が片付けの現場を担当するのかを決める
- 思い出の品や形見分けについて、全員が納得できるルールを作る
「勝手に捨てられた」という感情的なしこりを残さないためにも、リストを作成するなどして共有するのがおすすめです。
感情的になりがちな話題ですが、冷静にお互いの意見を尊重し、決定事項を書面に残しておくと後のトラブルを防ぐことができます。もし話し合いが難航するようであれば、弁護士や司法書士といった第三者の専門家を交えることも検討しましょう。
まとめ
実家じまいは、多くの人にとって初めての経験であり、その費用は時に大きな負担となります。しかし、今回解説してきたように、費用の全体像を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、その負担は大きく軽減できます。
最後に、重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- 「片付け」「解体」「売却」など、自分のケースで何が必要かを洗い出して総額の目安を掴む
- お住まいの自治体のウェブサイトを確認し、使える補助金がないか必ずチェック
- 「一般廃棄物収集運搬業許可」を持つ正規の業者を選ぶ
この記事が、あなたの実家じまいにおける費用への不安を和らげ、心穏やかに、そして賢く次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
もし、思い出の品の整理が終わり、残された家財の処分という具体的なステップに進む段階であれば、私たち不用品回収レスキューセンターが明確な見積もりと安心のサービスでお手伝いできます。お気軽にご相談ください。
電話、メール、LINEで24時間365日対応しております。
よくある質問
家の中の物を残したまま、解体業者にまとめて処分してもらえますか?
また、家財が残っていると解体作業の効率が落ち、人件費も余計にかかります。最も経済的な方法は、まず不用品回収や遺品整理の専門業者に依頼して家の中を空にしてから、解体工事を行うことです。
実家が遠方で、大量の荷物があります。どこから手をつければいいですか?
全体を一度に片付けようとすると途方に暮れてしまいます。その後、信頼できる専門業者に連絡し、現地での見積もりを依頼しましょう。プロが物量や状況を確認することで、具体的な作業計画と正確な費用が分かり、漠然とした不安が「解決すべき課題」に変わります。